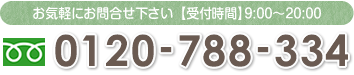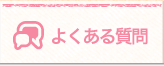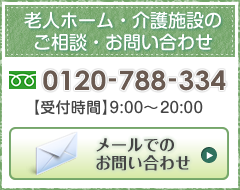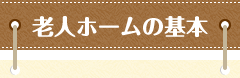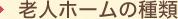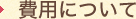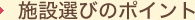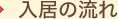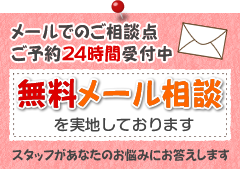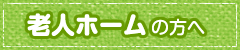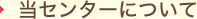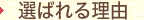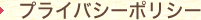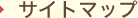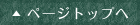ブログ
医療対応
大阪老人ホーム・介護施設紹介センターで入居相談を担当しております「山本」です。
老人ホームの中には、医療が必要な方でも受け入れてくれるところも多くあります。
特に、日中もしくは24時間看護師が常駐しているところであれば、受け入れの幅も広がります。
老人ホームのホームページやパンフレットを見ていると以下のような表記になっています。
認知症・・・ ○
ストマ・・・ ○
胃ろう・・・ △
痰吸引・・・ ×
概ね、「○」は受け入れ可能、「×」は受け入れ不可、「△」は応相談となっています。
しかし、「△」となっているところに関しては、特に注意が必要です。
応相談とはなってはいますが、老人ホームの人員体制等の理由で受入が
出来ないところもあります。特に、上記に記載しています“痰吸引”に関しては、
昼間だけでなく夜間も必要になる方もいます。
夜間の人員体制が、何らかの理由で整っていない状況にあるときは、
受け入れしてもらえないこともあり、注意が必要です。
当センターでは、日々、最新の医療対応の受け入れ状況を老人ホームごとの
最新情報の収集に努めていますので、
ご不明な点のある方は、一度お問い合わせ下さい。
大阪の老人ホーム・高齢者住宅をお探しの方は遠慮なくお問い合わせください。
大阪老人ホーム・介護施設紹介センター
0120-788-334
shoukai.center@gmail.com
嗜好品
大阪老人ホーム・介護施設紹介センターで入居相談を担当しております「山本」です。
老人ホームに入居するにあたって、自宅と同じ生活が送れることが一番うれしいですよね。
その中で、“嗜好品(お菓子・タバコ・お酒等)”に関しては手放したくないという気持ちが
大きいと思います。
嗜好品が医師から特別指示を受けていない状況であれば、老人ホームによって、
許容の基準はありますが、多くの施設についてはどのくらい許されるのかについて
書きたいと思います。
① お菓子(スナック菓子・プリン・アイスクリーム等)
基本的には、許されていますし、多くの老人ホームでは午後3時前後におやつの時間も
あります。
おやつの時間以外に食べるものに関しては、買い物(老人ホーム職員付添いの場合もあり)に
行った際に、好きなものを買い、居室で召し上がっている方もいます。
また、プリンやアイスクリームなどの冷蔵冷凍のお菓子については、
居室に冷蔵庫を持ち込んで、保存しています。
② タバコ
居室での喫煙は許されていない老人ホームがほとんどです。そのため、室外に設けられた
スペースで喫煙しています。自由にそのスペースに出入りでき1日に数回喫煙できる、
老人ホームもあれば、職員付添いのもとで喫煙しなければならないところもあります。
③ お酒
認められていません。ただ、「量を決めての晩酌程度なら対応しています」
というところもあります。
過去に、喫煙者の方で、老人ホームへの入居が難しいのではないか?と思ってらっしゃった
方がいましたが、喫煙可能な老人ホームを提案させていただき、今までの自宅での生活に近い
ことができると喜んでおられました。
※なお、上記の嗜好品については、個々の老人ホームの考え方によって、可能かどうか
変わってきます。今までに訪問した老人ホームの情報を基にお答えしたいと思いますので、
嗜好品の希望がある方は一度お問い合わせ下さい。
大阪の老人ホーム・高齢者住宅をお探しの方は遠慮なくお問い合わせください。
大阪老人ホーム・介護施設紹介センター
0120-788-334
shoukai.center@gmail.com
夫婦部屋
大阪老人ホーム・介護施設紹介センターで入居相談を担当しております「山本」です。
老人ホームの中には「夫婦部屋」がある施設があります。
部屋の広さは、ベットが2つおける広さになっており、概ね19㎡(約11.5畳)以上は確保
されており、中にはマンションのような感じで、2LDK以上の広さのところもあります。
夫婦で住む場合だと、2人で1室ずつ入居する時に比べて、
管理費や家賃が安く済むというメリットがあります。
(食費は2人分となります。)
ただ、夫婦部屋は、部屋数が少なく、空きが出てもすぐに埋まってしまう
傾向にあります。
そのため、夫婦で2部屋入居して、1部屋を寝室として、そして、
もう1部屋を居住スペースとして借りている方もおられます。そうなると、
通常は、家賃・管理費・食費が全て2倍かかってくるわけですが、
老人ホームによっては割引をしてくれるところもあります。
以前も、夫婦部屋で探してらっしゃる方がおられましたが、
たまたま希望地域に空きのある老人ホームがありませんでした。
ですが、上記のような方法で一時的に入居しましたが、
夫婦部屋に空きができ、優先的に移ることが出来たそうです。
夫婦での終の棲家をお探しの方も一度お問い合わせ下さい。
これまでに訪問した情報を基に、最良の老人ホームをご案内させていただきます。
次回は、日々の営業の中で様々な老人ホームを訪問させていただいておりますが、
その中での訪問記録について、老人ホームの館内の写真を交えながら
書きたいと思います。
よろしくお願い致します。
大阪の老人ホーム・高齢者住宅をお探しの方は遠慮なくお問い合わせください。
大阪老人ホーム・介護施設紹介センター
0120-788-334
shoukai.center@gmail.com
絶対に失敗しない有料老人ホームの選び方 ~第2章~
大阪老人ホーム・介護施設紹介センターで入居相談を担当しております「大塚」です。
本日は上岡榮信さんの著書「絶対に失敗しない有料老人ホームの選び方」第2章
「日本の高齢者の住まい方」から,ご紹介させていただきます。
~第2章~ 日本の高齢者の住まい方
「有料老人ホームと公共施設の違い」 (後編)
ここで,有料老人ホームとはどんなところか,簡単に説明しておきましょう。
有料老人ホームは,老人福祉法第29条において次のように定義されています。
「老人を入居させ,入浴,排せつ若しくは食事の介護,食事の提供又はその他の日常
生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与をする事業を行う施設で
あって,老人福祉施設,認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生
労働省で定める施設でないものをいう」
これでは,ちょっとわかりにくいかもしれませんね。要は住むための「居住機能」に,食事
介護,洗濯,清掃等の家事,健康管理など,日常生活に必要な「サービス機能」がセット
で提供される,高齢者向け住居と考えていただければいいと思います。
有料老人ホームの長所・利点としては以下のようなものが挙げられます。
≪有料老人ホームの長所・利点≫
「安心」 突然のケガ,急病のときでも職員が常にいる
医師,看護師,ケアマネージャー,ケアスタッフ,生活相談員,施設長,フロント職員
栄養士などの職員のチームワークがとれている。よいホームならば,職員の定着率が
高いので,よりチームワークはすばらしいものになる。
「安全」 バリアフリー等の設備,防犯等,また便利な生活拠点としてのメリット
ロビー,ラウンジ,ジャグジー付きの大浴場,レストラン,健康相談室などの共用施設
があり,台風や地震に対して建築基準上も安全に生活できる。
「規則正しい生活が送れる」
生活が規則正しく,生活にリズムがついてくる。食事も,栄養士が毎日バランスのよい
献立を考えてくれるので,健康になることが意外に多い。
「食事づくりのわずらわしさからの解放」
「自分の生活スタイルが守られ,エンジョイできる」
「集団生活の中で,入居者同士の交流が楽しめる」
「生活のマンネリを回避できる」
厚生労働省が発表した「老人関係施設の施設数」を見ますと,2012年10月現在
全国にある届け出済みの有料老人ホームは7519施設あり,それぞれのホームが
「居住機能」と「サービス機能」について,他のホームとの違いを打ち出しています。
たとえば,温泉付きやプール付きのホーム,ペットと同居できるホーム,24時間看護
師が常駐しているホーム,食事あるいはイベントに力をいれているホーム,高級ホテル
を思わせるような施設とサービスを併せ持つホームなど,多様なニーズに対応してサ
ービス内容も変化しています。また,介護が必要になってからも,安心して自分らしく
生活を楽しめるよう,個人の生活をサポートしてくれる有料老人ホームが増えています。
次に,有料老人ホームにはどのようなタイプ(施設類型)があるかということですが,介護
サービスの提供体制によって,「健康型」「住宅型」「介護付(一般型)」「介護付(外部サ
ービス利用型)」の4種類に分けられています。ホームで介護保険を利用して介護サー
ビスを受けたいのであれば,「介護付き有料老人ホーム」を選定してください。
以下,簡単に「健康型」「住宅型」「介護付」について説明します。
【健康型】
食事などのサービスが付いているホーム。介護が必要になった場合,契約を解除し退去
しなければならない。
【住宅型】
生活支援などのサービスが付いているホーム。介護が必要となった場合,入居者自身の
選択により,地域の訪問介護サービスを利用しながら,ホームの居室で生活を継続する
ことが可能。
【介護付】
介護や食事などのサービスが付いているホーム。介護が必要になった場合,ホームが提
供する特定施設入居者生活介護を利用し,ホームの居室で生活を継続することが可能。
介護サービスは有料老人ホームの職員が提供する。「介護付」と表示するためには,特定
施設入居者生活介護事業者の指定が必要。介護付にはホームの職員から直接介護サー
ビスを受ける「一般型」と,委託先の介護サービスを受ける「外部サービス利用型」がある。
終の棲家を検討するための際の参考にしてください。
大阪の老人ホーム・高齢者住宅をお探しの方は遠慮なくお問い合わせください。
大阪老人ホーム・介護施設紹介センター
0120-788-334
shoukai.center@gmail.com