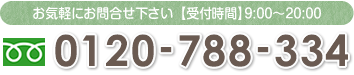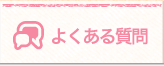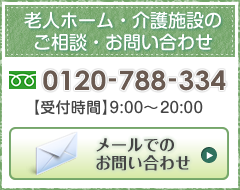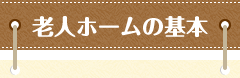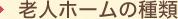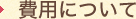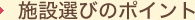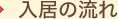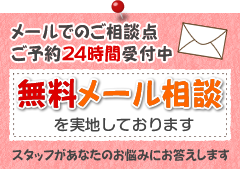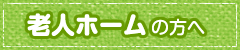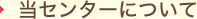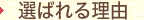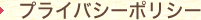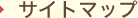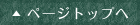ブログ
見守り、任意後見契約後の定期面会(見守り、任意後見契約後のお客様フォローの現場から)
本日は、見守り契約、任意後見契約をしたお客様との定期面会を行いました。
本日、午前に1名、午後からも1名と2名の方とご面会しています。
お元気な方は、散歩がてら私どもの事務所までお越しになられる場合も多いです。
お体の状況が低下してきている方は、私どもから訪問して面会しています。
午前中に面会した方は、お元気でして事務所までお越しになり近況を伺いました。
外出する機会になり、気分転換になるので、ちょうど良いとお話しになられます。
午後から面会した方は、老人ホームに入所していますので、私どもから訪問しました。
お体は不自由ですが、自分の意思は明確で意見は自分の言葉で表明されます。
面会時には、近況を伺いながら、判断能力や精神状態なども、ある程度は観察しています。
面会した際に感じたことや、発言されたことで特徴あることなどは、お客様ごとに作成したカルテに記録しています。
時系列に沿って見れるようにしておくと、その方の「一貫した意思」や「考えの変遷」が理解しやすくなると思います。
ポイント(点)を記録しておけば、点と点が繋がって一つの線になるような感じです。
ある発言をなさったとして、それが「一時の思いつき、きまぐれ」なのか?「一貫した意思・信念・期待・希望」なのか?
判然としないことはあります。
しかし、きちんと記録を残していると、その違いが推測できるようになり、どの意見や希望を優先して「お手伝いすれば良いか」が掴めます。
そうすることで、相談を受ける方も取り組むべき事柄の優先順位がついて、振り回されずに仕事ができると言うメリットもあります。
「何か困ってることはありませんか?」と質問するよりも、「雑談」の中で真意を探る方が良いこともあります。
その雑談の中で気づきを得れば、その点に関して質問を投げかける。深堀りする。記録する。
そして、その時期が来たと判断できる時にお手伝いする。
経験が浅いころは難しかったのですが、まだまだ修行が必要とは言え、少しづつ見える様になってきたと、最近は感じるようになりました。
サービス付き高齢者住宅(サ高住)の選び方(老人ホーム探しに関する相談の現場から)
サービス付き高齢者住宅の入居相談をお受けすることがあります。
サービス付き高齢者住宅は、少なくとも、「1日1回の安否確認」が義務付けられている高齢者向けの賃貸住宅と言って良いと思います。
法令上、要請されているのは、「1日1回の安否確認サービス」のみですが、実際には、非常に多くの施設で介護ヘルパーさんを常勤させていて、基本的には常勤のヘルパーさんに介護や生活援助をお願いすることになります。
また、看護師さんがいるところもありますし、理学療法士さんがいるところもあります。
なかには、24時間看護師を配置して、極めて医療依存度が高い方ばかりが入居している様なサービス付き高齢者住宅もあり、本来の制度設計とは少しズレますが、これも特徴の一つなのだと思います。
また、施設によっては、ヘルパーさんは敢えて常勤させず、ケアマネージャーさんを通じて外部から、自分の好きなヘルパーさんに来て頂くことが可能なサービス付き高齢者住宅も数は少ないですが存在します。
この様なタイプの施設は、ケアマネさんも、ヘルパーさんも、自分の気に入った人に依頼できますし、また受ける介護サービスも自分で決めることができますから、自己決定に対する意識が高い方には満足度が高くなると思います。
その一方で、自分が行った決定に対して、やはり自己責任を求められますので、入居する本人さん、ご家族さんにも一定のリテラシーが要求されると思います。
つまり、サービス付き高齢者住宅は、良い意味でも、悪い意味でも各施設ごとに特徴(個性)が大きく、サービス水準にかなりの開きがあると言うことです。
例えば、「夜間の訪室巡回が3時間に1回」の頻度で行われる施設もあれば、「夜間の訪室巡回は行われない。」と言う施設も存在します。
それ自体が、善とか悪とか言うわけではなく、「入居者の身体の状態に合っているか否か?」を検討するべきだと思います。
歩行が不安定でありながらも、居室のトイレは自分で行きたいと考えている入居希望者さんなら、夜間の訪室巡回はあった方が良いと思います。
さもなくば、仮に夜間に転倒した場合、自分でナースコールを押せなければ、朝まで転倒した状態から発見されない可能性が出てしまいます。
一方で、そのような危険がない入居希望者さんであれば、夜間の訪室巡回が無いことは、特に懸念事項にはならないでしょう。
サービス提供の水準が一律ではない多様な特徴をもつ「サービス付き高齢者住宅」を検討するのであれば、是非、老人ホーム選びの専門家に相談して欲しいと思います。
「自宅の近所にあるから」「知り合いが入っていたから」と言う理由だけで選択するのは、大丈夫なのかな?と心配になります。
老人ホーム選びの専門家であれば、その施設の特徴を知ってるはずですので、対面で一度相談してみられてはどうでしょうか。
インターネット上の情報や電話だけでは聞けない、「意見」がそこにあると思います。
認知症がある方はグループホームが向いているのか?(老人ホーム探しに関する相談の現場から)
「認知症がある場合は、グループホームを検討した方が良いのですか?」
相談を受ける中で、よくある質問です。
私どもの答えとしては、「入居者の性格による」です。
確かに、グループホームは認知症を患っておられる方に向け特化した施設です。
したがって、認知症の方に対する「向き合い方、接し方」については大変優れていると感じています。
しかし、そもそも入居される方が、グループホームに向かない性格である可能性もあります。
グループホームは、「グループ」と言うだけあって、「9名」を1つのグループ(ユニット)として、生活が進んで行きます。
そのため、やはり「一人の時間」が少なくなる傾向があります。
ご入居される方が、どちらかと言えば、以下のような性格の方。
「そっとしておいて欲しい」
「一人でいたい」
「イベントやレクレーションなどには参加したくない」
「集団行動が若いころから苦手だった」
この様なタイプや性格の方は、どちらかと言うとグループホームは向かないと思います。
老人ホームの入居相談をお受けした場合は、必ず、ご入居される方の「性格」をお聞きします。
時には、若いころの「職業」、「経歴」などもお聞きすることがあります。
その方の性格や属性に合った老人ホームをお探しすることが大切であり、入居後も施設に馴染みやすいと思います。
いくら、グループホームが認知症特化型の施設であるとしても、性格的に合わなければ入居する方にとっては、ただの苦痛でしかありません。
最初のご相談時に、心を開いて頂いて入居者さんに関する情報量を多く頂ければ、その情報量に比例して親和性の高い、老人ホームをお探しすることができる自信があります。
そういう意味では、相談を受けるこちらが、いかに「聞き出せる力」があるか?
その技量を求められていると思います。
「雑談」の中に真意があったり。
「身なり」や「自宅の状況」から、「性格」や「趣味」に関する仮説を立てたり。
経験に応じて、「聞く力」と「観察する力」の両方が付いてくるのでしょうか?
少しづつ相談に対する感受性が豊かになる様な気がします。
相談に応じる側にも「人間力」が必要と言うことになりますね。
その様な意味では、年齢とともに経験年数も上がりますので、あまり若手の相談員よりも、少しベテランの相談員の方がこの手の相談については、技量があるのかしれません。
老人ホームをお探しする専門家としての考え方(老人ホーム探しの現場から)
遠方にお住いのご家族からのご相談です。
自分の母親が大阪市に住んでいるが、入院して何とか自宅に帰ってきたけれども、やはり生活が立ち行かない様です。
今日も担当するケアマネージャーさんからご家族さん宛てに連絡があり、「やはり家で生活をして行くにはかなり大変だと思う」と言われた様です。
ご家族さんは、他府県にお住まいで頻繁に大阪に来ることは難しい様子です。
それでも、できるだけ早急に母親の入所できる施設の目途を付けたいと考えている。
その様な事情でした。
いつもであれば、私どもは対面を重視していますので、面談してお話をお聞きすることから始めることが多いです。
しかし、今回は、電話でのヒアリングを行ない、「場所」、「費用」、「入所する方の性格」、「病状」などをお聞きして、条件に収まりそうな施設を検討しました。
すると、いくつかの候補が上がってきたのですが、それぞれ特徴がある施設を4つ程度提案することにしました。
スピード重視するため資料は、全てPDFで電子化し、電子メールに添付してご家族さんへ送信しました。
今回提案した施設は、すべて私どもで、かつて、ご紹介し入居の実績がある施設ですから、施設の雰囲気も特徴も「私たち自身の言葉」でお話しして説明することが出来ます。
ここが、全国展開している紹介会社さんには無い、地域密着の紹介センターの強みだと思っています。
「自分の言葉で説明できること」それがパンフレットに記載されない、その施設に対する私どもの所見であり意見となると考えています。
「その施設と入居予定の方との親和性(相性)をどう見ているのか?」
「その施設をどう評価しているのか?」
「端的に自分の両親を入所させることが出来るのか?」
そういう視点で、お話しすることができなければ、ただの情報の羅列をしているだけであり、ある分野の専門家とは言えないと思います。
今回も送信するメールには、自分たちの言葉で施設に対する意見を付言しておきました。
もちろん、無理に誘導したりするつもりは一切ありません。
資料を見て、私どもの意見を聞いて最後に評価して決定されるのは、ご本人であり、ご家族です。
決定されたことは尊重します。
「自分の言葉で説明できない」「ただ言われた事をやっているだけ」では、ある分野の専門家とは到底言い難く、それでは、ご相談を頂いた方にも安心感を提供できません。
何となく、頼りない印象になってしまうのではないでしょうか。
ご相談を頂いた方が、「納得感のある決定」だと感じれるような、ご案内ができるように精進してゆきます。