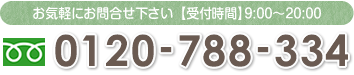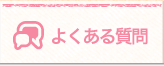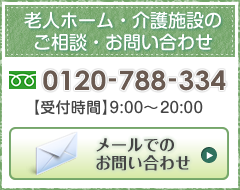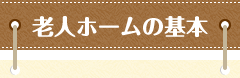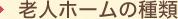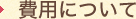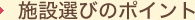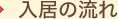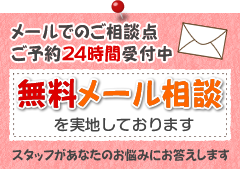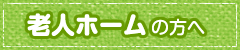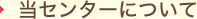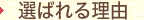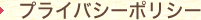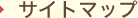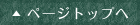ブログ
身元引受人、保証人としての老人ホーム入所契約の立会い(老人ホーム探しに関する相談の現場から)
本日は、私どものご紹介で老人ホームに入所されることになった方の入所契約の立会いを行いました。
今回のご相談者は、ご身内の方がおられません。入所に際しては身元引受人、連帯保証人が必要になりますので、私どもでお引き受けしました。
身元引受人や連帯保証人のことなど、気にしなくても希望する老人ホームに入所できるような世の中であれば良いのですが、現在のところは、そうもいかない様です。
連帯保証人には、「責任極度額」と言う「いくらまでの保証責任を負うか?」が定められます。
現在では、極度額の定めが無い連帯保証は無効になります。(詳しくは、弁護士さんか司法書士さんにご相談ください)
今回の契約では、月額費用の48か月分、約750万円程度が極度額になります。
つまり、支払いの未納などがあった場合は、保証人がその範囲で責任を負うことになります。
やはり、例え親戚がいても頼みづらいのは、間違いなく、それで普通だと思います。
一方で、保証人が必要だと言う老人ホーム側の立場も理解できなくはありません。
「支払いに未納などが生じた場合に回収できる目途もなく、安易に老人ホームからの退去も要求できない。」
とすれば、保証人に責任ある対応を求めなければ、身動きが取れないようになりますので。
すると、民間事業者である老人ホームとすれば、連帯保証人や身元引受人を求めるのは、ある程度は仕方ないことだとも思えます。
その様な事情から、頼れる身寄りが無い方に向けた民間の「身元保証サービス」や「保証人代行」のサービスが存在するのだと思います。
私どもでは、基本的に「身元保証サービス」や「保証人代行」のみをお引き受けすることはありません。
あくまでも、私どもを通じて老人ホームをご案内する中で、身元保証や保証人代行が必要であれば、その方に対してのみ、ご提案するものとしています。
やはり、お引き受けした限り、私どもはリスクを伴いますし、ご相談者がご逝去されるまで責任を持つ必要がありますから、前提に「信頼関係」が必要だと考えています。
そう考えれば、「初期の相談から関与し、一緒に老人ホームを探し、どの様な生き方、考え方をしておられる方なのか?」その方の個性や、私どもとの相性が判っていなければいけないと考えています。
「急いで入りたいので、保証人代行のみお願いします」と言ったご依頼やご紹介は、お声がけは有難いのですが、辞退しています。
今回のご相談者は、実は1年以上も前から面識がありました。
折を見て話を聞き、時間をかけて老人ホームを探しています。
ご相談者との会話や発言の要所などは、私どもでカルテに記録していて、意思に一貫性があり、認知症や精神的不安定さがないことは明らかです。
95歳になられますが、大変しっかりしておられ、契約に際しても受け身ではなく、気になることは自分から質問されます。
契約に関しての主要な重要事項の説明は理解されていて、場合によって、私どもから、少し補足説明するだけで十分な方です。
ご年齢から鑑みても、素晴らしいことだと思います。
ご相談者の「意思能力」、「資産」、「入居される施設」は、バランスのとれたものですし、私どもが有償サービスである身元引受人や連帯保証人をお引き受けしても、生活に支障を来すことはないと思いました。
ご相談者は、自らの直筆でしっかりと老人ホームの入所契約書に署名をされたのを確認しましたので、私どもも、身元引受人、連帯保証人として署名捺印しました。
これから、また長いお付き合いが始まることになります。
老人ホーム見学は比較して、誰かと議論することが大事(老人ホーム探しに関する相談の現場から)
老人ホームへの入所を検討するご家族様と2か所の施設の見学を同行しました。
入所する方は、お体は非常に元気ですが、認知症が日々進行していて、外出すると迷子になってしまったり。
短期の記憶もほとんど残っていない様子です。
ただ、「自分はしっかり出来ている。」と言う思いが強く、自分から老人ホームに入所されると言う気持ちになる様には見受けられません。
今回の見学は、「サービス付き高齢者住宅」と「グループホーム」の違う種別の高齢者施設です。
認知症と聞けば、「グループホーム」の方が良いかと思い込んでしまいますが、ご本人の性格や個性にもよります。
特に今回の方は、「自分はしっかり出来ている。」と思い込んでおられますから、ご本人がグループホームの様な雰囲気を受け付けない可能性はあります。
その様に考えた結果、2つのタイプやコンセプトが違う施設を見学して頂き、「ご本人にとって親和性のある施設はどちらか?」をご家族に考えてもらいたいと考えたのです。
実際に2つの老人ホームを見学してみると、全く雰囲気が違うことを改めて感じました。
「グループホーム」は、やはり、和気あいあいとした雰囲気が醸し出されており、介護スタッフさんの目の行き届きも充実している様に感じました。
施設にご本人を預けられるご家族としては、「安心できる」と感じるに十分ですし、ご家族もその様に発言されています。
すると、グループホームで良いのではないかと思いますが、実際に入所して生活をするのは、ご本人ですので、ご本人にとって親和性があるか、否かが大切です。
もう一度、ご本人の「性格や趣味・考え方」をプロファイルしてみました。
「デイサービスは、拒否して利用したことがない。」
「自分はしっかりしていると信じている。」
「どちらかと言えば気が短い」
「社交的と言うよりは部屋で手仕事をしていたい」
「身体能力は高く、徒歩で外出可能、ただし帰還できない」
この様な方でしたので、思い込みを捨て「サービス付き高齢者住宅」も見学してみることにしました。
見学してみますと、グループホームとは明らかに違います。
各自の居室の広さは、グループホームより「サービス付き高齢者住宅」の方が2倍以上も広いこと。
入居者の方も自分で歩ける方の方が多く、ご本人と近い身体状態の人が多い。
各居室にトイレが設置されているなど、生活空間としての独立性が高い。(通常、グループホームは、居室にトイレが無く、共用部分にある設備を共同利用します。)
今回、2つの施設を見学して、ご本人にとってどちらが良いか、私どもを交えて検討しました。
自尊心が高いご本人の性格を考えると、グループホームではなく、「サービス付き高齢者住宅」の方が親和性が高い。
日々のイベント、レクレーションなどは特別用意されていないことが気になりましたが、ご本人は、取り組むべき手仕事(自分の趣味)がある。
デイサービスなどは拒否されて利用していないことも加味すれば、過剰なイベント、レクレーションはご本人の負担になる可能性もある。
最終的には、グループホームではなく、「サービス付き高齢者向け住宅」を念頭に入所を進めて行く方針をご家族は選択されました。
今後、サービス付き高齢者向け住宅の相談員さんが、ご本人と面会してお話しする機会を作り、「相談員さんの目から見てサービス付き高齢者向け住宅での生活に耐えることができるか?」
を判断して頂く方針にしました。
今回は、2か所の種別やコンセプトの違う老人ホームを比較しながら見学しましたので、その違いを際立たせて感じるとこが出来たと思います。
少なくとも、2か所は見学を行って、もし可能であれば、その違いについて誰かと「議論」すれば、より「腹落ち」するようになります。
議論の相手がいなければ、私どもが、そのお相手になります。
「見学して違いを感じる。」と言う感性的、感覚的なものが、「誰かと議論する」ことで論理的に整理され、「腹落ち(納得・得心)」になるのではないでしょうか。
老人ホーム入所後の継続フォローについて(老人ホーム探しに関する相談の現場から)
本日は、私どもを通じて老人ホームに入所された相談者さんから、依頼があり同行の援助をしてきました。
依頼内容は、「老人ホームに入所する前に居住していた賃貸住宅の敷金の清算に行くので同行して欲しい。」とのことでした。
住宅の明け渡しは既に終わっており、あとは清算後に返還される敷金を受け取るだけなのですが、やはり一人では不安があるとのことでした。
この件では、特に法律的なトラブルはないと考えましたので、弁護士さんや司法書士さんに相談する必要はないと判断し、「同行援助」で対応しました。
本人さんと一緒に契約書に記載されている敷金の額を確認し、返還される金額を確認しました。
幸いにも、この件では相談者さんの負担で、修繕などを行う必要もありませんでしたから、契約書のとおりの返還を受ければ良い事案です。
何も大きなトラブルも無く、相談者さんも納得できる状態で、私どもが見守りながら敷金の返還を受け、領収書にサインをされました。
一見すると、この事案は、私どもの同行がなくても、相談者さんが一人で解決できた事案だと思います。
しかし、やはり少しでも、難しい事や言葉が出てきたら、動揺するし不安になるのも仕方のないことだと思います。
「この書類、サインしても良いのかな?」
「何となく、分かった様な、分からない様な」
この様な状態になった場合、誰かに同行してもらっていれば、心強いですよね。
良く分からないのにサインをしなければならない様な雰囲気になっても、同行者がいれば、「よく分からんなら、帰ろう!」と、その場の空気を割ってしまうことができます。
でも、ケアマネージャーさん、施設の相談員さんは、この様な場面に同行しては頂けないのが普通ですし、まず、その様な場面に慣れておられないので、お願いするのも少し違うと感じます。
一般的なお買い物の同行などであれば、ヘルパーさん、ケアマネージャーさんにご相談を頂いた方が良いと思いますが、やはり職域と言うか、それぞれに活動フィールドが違いますので。
今回のような、「敷金(保証金)の精算の立会い」とか「退去の立会い」とか「争いのない契約ごとの立会い」の様なこと。
その他に「公証役場での遺言書の証人・立会人」なども、私どもがお手伝いできる領域になります。
お一人でなされるのが不安な方は、有償のサービスですがお気軽にご相談頂ければご対応をしていますので、お声がけ頂ければと思います。
気持ちに沿った良い相談対応とは?(老人ホーム探しに関する相談の現場から)
本日は、午前と午後に別けて、2名の方の老人ホームの見学を同行しています。
午前中の方は、数年前までお住まいであった地域の老人ホームをご提案しました。
見学はご本人と一緒に伺いましたが、好きで老人ホームに入所したい訳ではないことは分かっていました。
病気になってしまって、自宅では暮らして行くことが出来なくなり、仕方なく老人ホームを選択することになった方です。
年齢も比較的ですがお若いこともあり、その気持ちも理解できます。
「消極的同意型」の老人ホーム探しも現実にはあります。
むしろ、こちらの方が多いのかもしれません。
誰しも本当は自分の家で暮らし、自由に行動して、気兼ねのない生活を送りたいと思います。
そう考えれば、自分の中で「気持ち」や「条件」に折り合いを付けて、入所することが殆どではないでしょうか。
そう考えれば、100点満点の老人ホーム探しは出来ないとしても、少しでも「腹落ちする」様な老人ホームとご縁を持って欲しいと本当に思っています。
今回の相談者と「雑談」していると、やはり病気になる前に住んでいた地域の話になると表情が明るくなることは、以前から観察していました。
その縁のあった場所にある老人ホームであれば、少しでも「腹落ちする」かも知れないと仮説を立てました。
ただ、反対に「元気だった当時の自分と不自由になった今の自分を比べて、卑屈になってしまうことはないか?」も少し心配ではありました。
「雑談によって得られた何気ない情報」
「相談者の表情や使用する言葉」
「もし、自分ならどうするか?」
この相談者の方に関しては、ご縁のあった場所(地域)の老人ホームが良いと感じる。
この様な推理を重ねた上で、見学にお誘いしました。
結果としては、相談者には、喜んで頂けて、前向きにご検討して頂く方向となりました。
ただ、この相談者に関しては、喜んで頂けましたが、全員がそうなるとは限りません。
あくまでも、相談者ごとに意見も考え方や感じ方も違うのだと思います。
どうすれば、相談者に応じた良い対応ができるのでしょうか。
いまでも試行錯誤してます。
「相談者の何気ない会話を含めて、話しをよく聞くこと。」
「表情や仕草、話し方、語気などを含めて観察すること。」
結局は、「相談者の人間性や人格に興味を持つこと」が良い相談対応の基本なのかも知れないと思います。