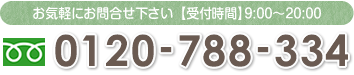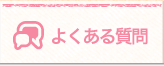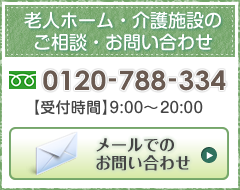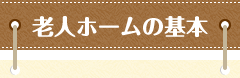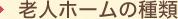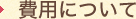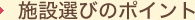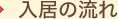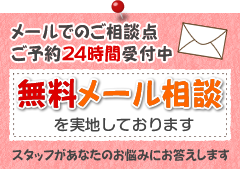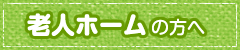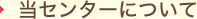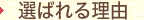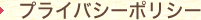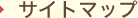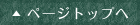ブログ
少し「こだわり」がある、ご相談者の施設の見学をお受けして(老人ホーム探しに関する相談の現場から)
この度の相談者さんは、他の紹介会社さんを通じて以前から、老人ホームを探していたようですが、なかなか思うところが見つからないので、私どもにも相談があった方です。
お話をお聞きすると、施設を探すにあたっては、いろいろと拘りが感じられ、それを全て加味してしまうと、なかなか見つからない様です。
今回は、特に強い希望のみをお聞きして、そこを集中的に検討した方が良いと感じましたので、一度、お話を丁寧にお聞きしてみました。
すると、ご本人の希望する一番のこだわりは、「部屋の明るさと広さ」あるいは「明るい雰囲気の部屋」であることを掴みました。
その他にも、「場所」や「地域」などが当初は、お話しに挙がっていましたが、よく整理して行くと、それは、「ご家族(親族)」の意向であり、ご本人の拘りではないようです。
いままで、6件以上の老人ホームを見学して、最終的な決定に至ってないことを考えると、今回も、条件の全てを満たすことを期待させて見学をしても、良い方向に進まない様に感じました。
ご家族さんも、なかなか行き先が決まらないことに不安と苛立ちを感じているようです。
そこで、ご家族さんともお話しし、「場所(エリア)」の優先順位を少し下げて、実際に生活するご本人の希望を最優先で検討して頂けるようにお願いしました。
ご家族さんも、かなりの件数を検討してきたのに思う様に決まらない経緯もあり、「本人が納得するところなら、それで良い」と私どもの提案に同意して頂けました。
次に、今まで見学してきた施設について、質問してみると、どうやら「住宅型」有料老人ホームばかりを見学してきている様でした。
また、場所も利便性を優先してのことで、大阪市内の中でも中心部に近く、駅にも近いところを見学してきておられました。
見学した施設を参考にして、ある気付きを得ました。
まず、ご本人は、部屋の広さに拘りがある発言していますが、「住宅型」は、平均的に居室面積が15㎡以下であることが多く、部屋の広さには期待が持てません。
つぎに、利便性の高い中心部は、施設の周辺に建物が密集しており、「採光」が十分で無く、また居室の窓を開けても、「圧迫感」を感じてしまう可能性があるのではないか?
ご本人が期待する「部屋の明るさと広さ」または、「明るい雰囲気」の居室を優先して検討するのであれば、少し不便でも周辺に建物が密集していない郊外地の方が良いのではないか?
そこで、今まで見学したことが無かった、居室の面積が18㎡以上あり、居室にキッチンがある「サービス付き高齢者住宅」を検討候補にあげました。
この施設は「バルコニー」がお部屋にあり、認知症が無い方であれば、自由に利用することが可能です。
東向きで採光も良く、周囲に建物が密集しておらず眺望が抜けています。(但し、少し辺鄙に感じますが)
バルコニーに出れば、居室にいながら「外の雰囲気」を感じることが可能です。
もう既に複数の施設を見学してこられた経緯がありましたので、まずは、この1件の施設を見学し感想を聞いて、必要に応じて他を検討する方針としました。
すると、意外でしたが、ご見学の結果、ご本人さんから、「この施設でお願いしたい」と自ら発言されました。
念のために理由を聞いてみますと、やはり、居室空間の広さ、遮られない眺望が良いと感じたようです。
駅から徒歩15分はかかりますので、決して便利とは言えないのですが、ご家族さんも今まで、一度も自分から同意したことがない、ご本人が自分から、「ここでお願いしたい」と発言されたことに驚かれていましたし、多少不便でも生活をするのは、本人だからとご理解を頂けたのです。
老人ホームをお探しする際には、いろいろな希望や条件が出ることがあります。
しかし、その全てを受容できる施設は無いことも多く、この場合は優先順位をつけるか、あるいは、「できること」と「できないこと」を分類して、いわゆる「希望の交通整理」が必要になります。
いくら、親切で丁寧で、優しくても「行き先」が決まらなければ、老人ホーム探しの専門家として、仕事をしたことにはなりません。
また、不必要に多くの施設見学に連れまわし、ご家族や本人の時間を奪うことになってしまいます。
きちんと、ポイントを押さえた施設を数件見学して、比較して頂く必要があると思います。
意義のある見学をして頂くためにも、
「よく聞いて」
「仮説を立て提案し」
「根拠と意見を述べることができる」
老人ホーム探しの専門家としての仕事をしなければいけないと改めて感じました。
生活保護を受けている方のお引越し手続き(老人ホーム探しに関する相談の現場から)
生活保護を受けておられる方が老人ホームに入所される場合、生活保護費から「荷物の移送費用」や「家財道具の処分費用」が給付されます。
生活保護を受けておられる方にとって、時として、数十万円以上が必要な荷物の移送や処分費用は、簡単に用意できる金額ではありません。
ですから、基本的には、ケースワーカーさんに相談して、これらの費用の給付の申請を行います。
「荷物の移送費用」か「家財道具の処分費用」か、どちらか一方のみしか申請させてもらえない。
と言うローカル・ルールがある。とを聞いたこともありますが、この取り扱いには特に根拠はありません。
ですから、必要に応じて「荷物の移送費」も「家財の処分費」も申請は可能であるのが原則だと思います。
また、複数の見積もりを取得して、最安値を提示した業者さんに依頼すること。
大阪市の場合は、基本的に引っ越し業者、3社分の見積もりを取得して提出する取り扱いとなっています。
家財道具の処分に関しては、大阪市の指定の産廃業者の中から2社分以上の見積もりを提出します。
以上のようなルール(取り扱い)に沿って申請すれば、「荷物の移送費」や「家財の処分費」を生活保護費から給付されることになります。
引っ越し業者の見積もりを3件も依頼することも大変ですし、産廃業者などは、区役所で一覧表をもらえますが、正直に言いまして、どこに連絡すれば良いのか?
分からないのが普通です。
この様な時にも、老人ホーム探しの専門家である「紹介センター」にご相談ください。
スムーズに引っ越しを進めることが出来ように助言をしています。
また、行政や業者さんとの窓口となって取り纏めをしてくれることもあります。
私どものご案内で、老人ホーム探された相談者さんについては、依頼があれば、私どもが行政と業者さんとの窓口になって、連絡や調整などを行います。
結果として、その方がスムーズに手続きが進んでいくようにも感じます。
老人ホーム入居とお引越し手続き(老人ホーム探しに関する相談の現場から)
老人ホームに入所するに際しては、お荷物の移送や家財道具の処分が見込まれます。
気を付けて頂きたいことは、「家財の処分」に関する費用が高額になることです。
自分で「大型ごみ」として市に回収に来て頂けば、数百円から数千円の費用で済むこともありますが、
自分で大きな備品を運び出す必要があり、かなりの重労働です。
大量の不用品を自分で運び出すのは、重労働であるだけでなく危険ですので、多くの場合は、不用品処分の業者さんにお願いすることになります。
処分業者さんの価格に決まりはありませんので、価格には、かなりの開きがあると感じます。
なかには、悪質な業者さんもあると聞いたことがありますので、注意して欲しいと思います。
かなり以前ですが、100万円近い見積もりを拝見したことがありましたが、別の業者さんで見積もりを取り直したら、40万円以下の金額の見積もりが出てきたこともあります。
別に100万円近い、見積もりを提示した業者さんが悪いわけではなく、見積もり金額には、かなり「幅」があることがあることを知って欲しいのです。
ひょっとすると、100万円の見積もりを提示した業者さんは、「仏壇のお性根抜き」などの費用が含まれていたのかも知れません。
お部屋の清掃も行い、それらの費用も含まれているのかも知れません。
高額な見積もり自体が「悪」なのではありません。
見積もり内容が、自分が求めている事と合っていれば良いのです。
ポイントは、やはり、
① 複数の業者さんに見積もりを依頼すること。
② 可能であれば、誰かに同席(立会い)をして頂いた方が良いと思います。
一人ですと、密室の空間の中での交渉になりますので、何となく心細いと感じるのではないでしょうか。
私どもに同席(立会い)の依頼があれば、時間が許す限りは同席(立会い)しています。
私どもの過去の経験から、このくらいの処分量なら提示を受けた見積金額が適当かどうかは、感覚的にわかります。
見積もりに来られた業者さんにお断りするのが、気が引けるのであれば、私どもから、お断りのご連絡をすることもあります。
また、多少ですが価格の調整をお願いすることもあります。
価格の調整については、あまり期待されても困りますが、受けるサービス内容を整理すれば、多少は融通がつくこともあります。
無理な値引き交渉などは行えませんし、お願されてもお断りしていますが、本当に必要なサービス内容を整理すれば、多少の値下がりは見込める場合もあるのではと思います。
お引越しや不用品の処分業者さんをお探しになる場合は、参考にして頂ければと思います。
老人ホーム入所に伴う生活保護の手続き(老人ホーム探しに関する相談の現場から)
先日、老人ホームの見学をご一緒した方のアセスメントが終わり、入所への方向が決まりました。
ただ、今回のご相談者は、大阪市の某区で生活保護を受けておられますので、生活保護を担当するケースワーカーさんとの話し合いが必要になります。
ケースワーカーさんも人間ですから個性もそれぞれ違いますし、また同じ大阪市でも区によって、かなり雰囲気と言うか温度感が違うと感じます。
大阪市の中でも区によって、ローカルルールの様なものがあったりする様です。
大体のケースワーカーさんは親切な方が多く、嫌な思いをしたこと記憶は殆どありません。
強いて言うならば、「敷金が不要な老人ホームを探すように」など、言われたこともありますが、この時は少し変だと思いましたので、弁護士さんや司法書士さんにお願いして相談に同行して頂いたことがあります。
結果として、敷金は必要と判断され、きちんと出して頂けました。
生活保護を受けながら老人ホームに入所する為には、担当のケースワーカーさんに相談に行き、入所しようとしている施設の「重要事項説明書」と言う資料を提出します。
その施設が生活保護を受けていても生活をして行ける施設なのかをケースワーカーさんが確認します。
その他にも、かかりつけの医師の意見書を取り寄せて、老人ホームへの入所が本当に必要かを会議にかけて判断します。
ポイントは、ケースワーカーさんが独断で決めている訳でないと言うことです。
あくまでも、会議にかけて決裁を得ているのです。
ケースワーカーさんは、我々から提出を受けた資料、医師の意見書を基に稟議をあげて、最終的には会議の上で決裁されているのです。
お気付きになられた方もいるかもしれませんが、ケースワーカーさんから早く老人ホームへの入所の承諾を得たければ、ケースワーカーさんが仕事をやり易くしてあげることが、最も合理的です。
「整理された資料を提供すること」
「事実関係を整理して説明すること」
「要望(主張)を明確に伝えること」
さらに、以下は、一般の方は難しいので、できればですが、
「要望(主張)の妥当性を支持する根拠を添えること」
文献を当たれば、法令や通達などは、たくさん出てきます。(もちろん、ある程度、法令・通達を理解できることが前提になりますが)
ケースワーカーさんが、全ての法令、通達を網羅していることはあり得ないので、自分の要望(主張)を支持する法令、通達を示せるならば、きちんと根拠があっての相談だと認識できますので、ケースワーカーさんの取り組み方も変わります。あまり前例が少ない事例や、込み入った事情がある事例を相談するのであれば、なおさら意識した方が良いと思います。
このあたりを少し難しく感じるならば、生活保護のことに詳しい、老人ホーム探しの専門家(紹介センター)などを頼った方が良いと思います。
ただ、全ての紹介センターさんが、きちんと生活保護のことを勉強している訳でないかもしれないので、その辺りは留意してください。
事務的にお手伝いをしてくれる紹介センターさんもありますが、労力的な負担はなくなるので助かりますが、それだけでは、対応できないことも時にはありそうです。
やはり、私どもとしては、老人ホーム探しの専門家を自称する以上、知らないことや、はじめて出くわす事例も出てきますが、きちんと裏付けとなる根拠も含めて勉強しておきたいと考えて活動しています。