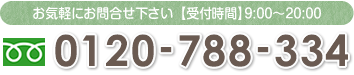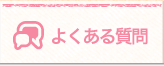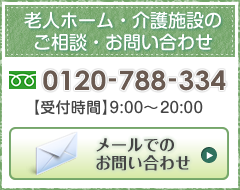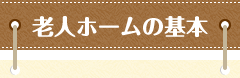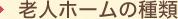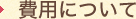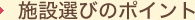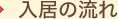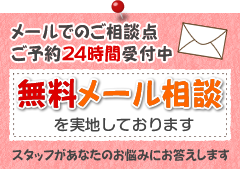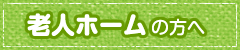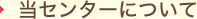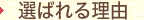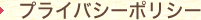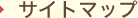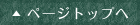ブログ
身元保証人・任意後見人の役割とは?緊急時の医療対応事例(身元保証人と任意後見人としての相談の現場から)
今回は、私たちがご支援している自立型シニアマンションにお住まいのご利用者様の事例をご紹介します。ご家族がいらっしゃらないため、当社で身元保証人(任意後見人)をお引き受けしています。
突然の体調不良、任意後見人はどう動く?
ある日の夕方、施設から「ご利用者様がみぞおちの痛みを訴えている」と連絡が入りました。時間外なので、救急外来にお連れすべきか迷う状況です。
幸い、ご本人様から直接電話をいただき、安静にしたら痛みは治まったので、ひとまず様子を見たいとのこと。
電話でご本人の声を確認し、緊急性は低いと判断。もし痛みが再発して眠れないようであれば、いつでも救急外来に付き添うことをお伝えし、夜間の対応に備えました。
高齢者の救急受診における課題
高齢者の時間外・救急外来受診は、身元引受人(後見人)やご家族と連絡が取れない場合、診察を断られるケースがあります。
これは、認知症などで十分な問診が難しい場合、医療事故のリスクが高まるためです。
任意後見人や成年後見人には、医療行為への同意権はありません。しかし、ご本人の意思を尊重し、希望する医療が受けられるようサポートする重要な役割があります。
任意後見人だからこそできる医療サポート
「後見人は医療行為に対する同意権を持たない」という原則を守りつつ、私たちができることは何か。
今回のケースでは、ご利用者様の病歴や通院先を事前に把握していました。また、延命措置を望まないというご本人の公正証書による書面も保管しています。
このように、ご本人の状況を詳しく知る私たちが付き添うことで、本人の意思決定をスムーズに引き出すことが可能になり、結果として医師も安心して診察に臨むことができるのだと思います。
ご利用者様に寄り添う、柔軟な対応を
最終的に、ご利用者様には「痛みが増したら遠慮なく連絡を」とお伝えしました。
私たちは、肉親として家族ではありませんので、それと同じような対応を期待されても、その期待には応じることができません。
私たちにも、個人としての生活があり、家族がありますので、対応しきれない部分は確かにあります。
ただ少なくとも、私たちは、単に身元保証を事務的に行うだけでなく、一人の人間としてご利用者様の状況に寄り添い、柔軟な対応を心がけるように可能な限り努力したいと考えています。
緊急時の医療サポートもその一つであり、利用者様が安心して暮らせるようにするには、何ができるのかを考えて行きたいと思っています。
急ぎの施設探し、どうする?7日で入居先を見つけた事例から学ぶ「良いタイミング」の見つけ方(老人ホーム探しに関する相談の現場から)
急な入院で退院日が迫っている、介護認定の結果が出ていない…。そんな厳しい条件で入居先を探さなければならない時、焦ってしまいますよね。
今回は、通常なら難航しがちな状況で、わずか7日間で入居先を見つけることができた事例を通して、「良い施設と出会うための秘訣」をお話しします。
「急ぎ」の施設探しを成功させる2つのポイント
お急ぎでの施設探しは、本来お勧めできることではありません。なぜなら、時間をかけて見学し、ご本人やご家族に合った施設をじっくり選ぶことが、その後の生活の満足度につながるからです。
しかし、やむを得ない事情がある場合もあります。そんな時に、希望の施設を見つけるには何が必要なのでしょうか。この事例では、主に2つのポイントが鍵となりました。
1、多くの施設に、声がけすること
これは当たり前のことのように聞こえるかもしれませんが、施設側には様々な事情があります。例えば、
- 急な退去で空室が複数発生し、早く埋めたい
- 特定の居室が長期間空いており、何とか入居につなげたい
など、施設の経営状況やタイミングによって、通常よりも柔軟な対応をしてくれることがあります。
今回のケースでも、介護認定が未決定という厳しい条件でしたが、数多くの施設に声をかけることで、偶然にも「今なら受け入れられる」というタイミングの施設を複数見つけることができました。
2、「タイミング」を察知するための、信頼関係
ただ数多く声をかけるだけでは、この「良いタイミング」を掴むことは難しいでしょう。なぜなら、施設の空室状況は経営に直結する機密性の高い情報だからです。インターネット上の情報や、初めて連絡する紹介会社には、本当の空室状況や内部事情を詳しく話してくれることは少ないのが現状です。
私たちが今回、良いタイミングを察知できたのは、日頃から施設長さんと本音で話せる関係性を築いていたからです。
- 「実は今、特定のフロアの空きが多くて困っている」
- 「現在の介護スタッフの負担を考えれば、すこし介護度が低いお元気な入居者を募集したい」
- 「常勤する看護師さんにもっと頑張ってもらいたいので、医療行為などを積極的に必要とする介護度の重い入居者を募集したい」
といった、施設の正直な事情を聞き出すことができたからこそ、一般的なルールでは難しい条件のご相談者様でも受け入れを検討してもらうことができたのです。
インターネットでの施設探しとの違い
これは、インターネットで多くの施設情報を提供する紹介会社には難しいアプローチです。私たちは、地域に密着し、実際に足を運んで施設長と顔を合わせることを大切にしています。施設長と直接会って話すことで、施設の雰囲気や理念を肌で感じ、深い信頼関係を築くことができるからです。
厳しい条件で施設を探す必要がある方は、インターネット上の一般的な情報に頼るよりも、地域の施設と密接な関係を築いている対面で相談できる紹介会社にご相談されることをお勧めします。
今回のご相談者様も、複数の施設長と本音で話を進めた結果、わずか7日間で4つの候補が見つかり、無事に入居先を決めることができました。
老人ホーム入居支援の舞台裏〜生活保護受給者のケースから学ぶ調整・交渉術と信頼関係の重要性(老人ホーム探しに関する相談の現場から)
本日は、老人ホームへのご入居の立ち会いという役割を担いました。
今回の相談者様は、以前に別の紹介会社にご相談されていた経緯があり、詳しい事情は不明ですが、長い間、入所できる老人ホームが決まらなかったという状況に直面されていました。このような背景もあり、私どもとしては、ご入居が無事に完了するまで、契約の立ち会いも含め、最後までしっかりとサポートさせていただきたいという強い思いがありました。
高齢のご家族を支える支援の重要性
ご相談者様にはお子さんがいらっしゃらず、ご兄弟の皆様が手分けしてご本人を支援されていました。皆様もご高齢になられているご様子で、その大変さがひしひしと伝わってきました。だからこそ、私たちが力になりたいと強く感じました。
生活保護に関すること、入所の契約、費用に関することなど、複数の課題が重なると、ご本人様やご家族様が混乱されるのは当然のことです。特に今回は「生活保護」に関する部分で、私たちがご家族様やご本人様の窓口となり、関係機関との連絡・調整を引き受けました。
生活保護受給者の老人ホーム入居における費用と交渉のポイント
老人ホームへ入所する際には、通常、敷金や日割り家賃が必要となります。これらの費用は生活保護費から支給されることがありますが、ケースワーカーさんを通じて申請を行い、すぐに支給されるわけではありません。一定の審査期間が必要となります。
今回は、どうしても早期に入所する必要がある事情がありました。通常であれば、敷金や日割り家賃は入所前に用意するか、入所当日に支払うのが原則です。しかし、私どもは老人ホーム側と粘り強く交渉し、入居後の後払いを特別に認めていただくことができました。
この交渉が成功した背景には、以下の重要なポイントがあります。
- ケースワーカーさんとの綿密な連携: 確実に申請した費用が支給されるか、事前に確認を取り合いました。
- 老人ホーム側との信頼関係: 普段からの連携を通じて築き上げてきた信頼関係が、今回の交渉を円滑に進める上で非常に大きな要因となりました。
調整役としてのやりがい
このようなケースでは、「ご家族(ご本人)と老人ホーム」、あるいは「ご家族(ご本人)とケースワーカーさん」といった多角的な関係性を円滑に調整していくことが求められます。これは想像以上に神経を使い、大きな緊張感を伴う業務です。もし私たちのミスリードがあれば、ご家族様や老人ホームにもご迷惑や不安を与えてしまうことになりかねません。
しかし、このような複雑な調整がうまくまとまり、ご家族様に心から喜んでいただけた時の達成感はひとしおです。これこそが、この仕事の大きなやりがいであると感じる一面です。
老人ホームの入所に関するご相談に応じることの**「難しさ」と「やりがい」は、まさに私たち支援者側の人間力(胆力)**に比例すると言えるでしょう。地道な経験を積み重ねることでしか得られない、奥深い仕事だと改めて感じています。
老人ホーム入居時の賃貸退去トラブル!「原状回復義務」の思わぬ落とし穴と専門家連携の重要性(老人ホーム探しに関する相談の現場から)
老人ホームへのご入居が決まり、現在のお住まいを引き払う際に、賃貸住宅にお住まいだった場合、大家さんへお部屋をお返しする必要があります。この退去時、思わぬトラブルに発展しやすいのが「原状回復義務」です。
「原状回復義務」とは?知っておきたい基本と注意点
お部屋に目立った破損がなければ問題ありませんが、もし不注意で設備を壊してしまったり、汚してしまったりした場合は、この「原状回復義務」に基づき、修繕費用の負担を求められることがあります。
一般的に、通常の使用による自然な劣化や故障については、借主が修繕費用を支払う必要はありません(契約内容によります)。しかし、借主の不注意や故意による破損と判断された場合は、その修繕費用を負担しなければなりません。
敷金・礼金ゼロ物件の落とし穴
賃貸契約時に「敷金」を預けていた場合は、修繕費用が発生しても敷金から差し引かれるため、持ち出しが少ない、あるいはゼロで済むケースもあります。しかし近年増えている「敷金・礼金ゼロ」の物件では、退去時に修繕費用の負担を求められた場合、その場で高額な支払いを求められる可能性があります。
数万円程度ならまだしも、10万円を超えるような請求は、年金生活が主となる高齢のご利用者様にとって大きな経済的負担となります。
ご利用者様の不安を解消するために私たちができること
先日、私たちがご支援させていただいたご利用者様も、賃貸物件の大家さんから修繕費用の指摘を受けそうな状況で、金銭的に余裕がなく、また大家さんとの交渉も苦手とされており、大変ご心配されていました。
私たちの仕事は、老人ホームのご紹介や入居支援が主であり、退去時の具体的な交渉を代行することはできません。単なる退去の立ち会いであればお手伝いできることもありますが、費用の負担に関する交渉に介入することは、専門外であり、法的な問題も生じる可能性があります。これは、ケアマネージャーさんや医療ソーシャルワーカーさんも同じだと思います。
しかし、ご利用者様が言われるがままに不当な費用を請求されたり、退去後も頻繁に大家さんからの連絡に悩まされたりすることは、老人ホーム入居後の新しい生活の安定を著しく阻害してしまいます。
そこで今回、私たちは司法書士さんに交渉の窓口をお願いすることにしました。
専門家連携の力:ご利用者様の心理的負担を軽減する
司法書士さんには、法的な視点から「支払う必要のないもの」と「支払う必要があるもの」を明確に整理していただき、必要な支払いについては誠実に対応する方針で進めています。
このような専門家を介した交渉窓口を設けることで、ご利用者様の心理的な負担は大きく軽減されます。不必要な支払いを防ぎ、スムーズな退去を実現することは、ご利用者様が安心して新しい生活をスタートするための重要なステップです。
私たちは、このように他分野(特に士業)の専門家との連携に力を入れています。ご利用者様一人ひとりの状況に合わせ、最適なサポートを提供できるよう、これからも根気強く連携体制を強化していきます。