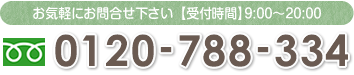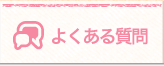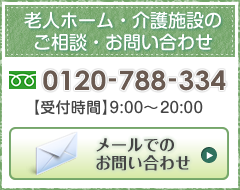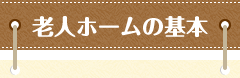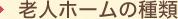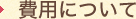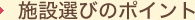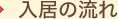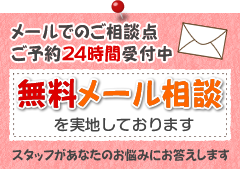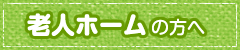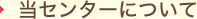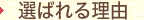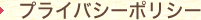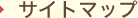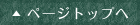ブログ
老人ホーム探しと住宅の明け渡し交渉(法律相談を伴う老人ホーム探しの現場から)
ケアマネージャさんからご相談で老人ホームを探すことになりました。
私たちの会社は、弁護士や司法書士との連携を特徴に打ち出していますので、相談内容は、ただの老人ホーム探しではない事案が多いです。
もちろん、ごく普通な老人ホームのご紹介もしていますが。
他の紹介会社さんでも専門家の紹介はしているかも知れませんが、それと違うのは、相談の内容によっては初めから専門家と一緒に動いていることです。
今回の相談事案も、入院や認知症の進行など理由はいろいろあったのですが、金銭管理ができず、家賃などの支払いが数か月分以上滞納している状態でした。
相談者の預貯金よりも、滞納した家賃など債務の方が多く、債務整理が必要です。
この様な事案では、紹介会社としては老人ホームの紹介はできますが、それ以外の債務整理の相談や話し合いに参加は出来ません。
この様な事案では、最初から司法書士や弁護士に同席してもらい、その場で解決方針を立てて貰います。
また、時として最初から専門家に窓口になってもらい、交通整理をおこなって交渉などをして行きます。
今回の相談も、老人ホームを探しながら、家賃などの滞納分について解決が必要です。
さもなくば、老人ホームに入所した後に取り立てがきたり、預貯金に差し押さえがあったりすると、老人ホームの費用が支払えなくなり、すぐに退去しなければならない可能性もあるからです。
今回も、法律の専門家に代理人として交渉の窓口になってもらい、債務整理について解決を目指しながら、老人ホームを探すことになりました。
老人ホームを見学するには当たっては、相談者に解決するべき債務があることは正直に話します。
しかし、しっかりと解決への目途や道筋が説明できますので、借金や紛争を抱えていることが原因で老人ホーム側からお断りされたことはありません。
今回は、2件の老人ホームを見学し、当社のご案内した施設へご入居して頂くことができました。
また、債務の問題についても、法律専門家を通じて相手方に事情を丁寧に説明して頂き、少しだけ和解金をお支払することで、その他の債務を免除して頂くこともできました。
やはり、このような事案は早い目に弁護士さん、司法書士さんなどの専門家に協力を要請した方がよいです。
ご本人やケアマネージャーさんが相手方と話されても、感情がこじれてしまいがちです。
紹介会社が代わりに話し合うことも行ってはいけません。(弁護士法や司法書士法に違反する犯罪行為です)
ご本人や近しい方であれば、気後れして言えないことも第三者の代理人だからこそ、言えることもあります。
また、ご本人であれば、「後ろめたさ」もあり、この様な話し合いにも慣れていないこともあり、ストレスも溜まります。
弁護士さん、司法書士さんの費用がかかるのではないか?
もちろん、全てが無料ではありません。
但し当社のお願いする弁護士さんや司法書士さんは、「法テラス」と契約していますので、法テラスを利用すれば、生活保護など一定の条件を満たす方は、費用のほとんどが無料になることもあります。(すべての事案で無料になるわけではありませんので、詳しことは個別にご相談ください。)
気になることが、もしあればご連絡ください。まずお話だけでもお聞きします。
緊急連絡先になってくれる人はいますか?(緊急連絡先の引き受け業務から感じること)
80代のお元気な方です。
この相談者の方は、お元気で自分のマンションにお住まいになっておられます。
とても、アクティブな方で先日、フィットネスクラブに入会しようと考え見学に行ったそうです。
施設の設備や自宅からの距離なども気に入り、入会を決めました。
ところが、入会するにあたり「緊急連絡先」を記載する必要があるようです。
相談者は、結婚歴がなく、兄弟はいますが疎遠で、遠方に住んでいるので、緊急連絡先として記載することができません。
フィットネスクラブの方のお話しでは、ある程度のご年齢の方が入会する場合は、急な体調の悪化、場合によっては緊急搬送に備えて、緊急連絡先を定めて頂いているようです。
説明の趣旨からすると、単に形式的に名前を記入すれば良いのではなく、「いざ」と言う際にはきちんと対応できる方である必要があるようです。
相談者には知人はいますが、やはり負担をかけたくは無く、お願いすることは出来ないと思われ、入会を断念して帰ってこられたとのことです。
老人ホームへの入所、病院への入院などで、身元引受人や緊急連絡先が必要とされることは多く、殆どの老人ホーム、病院で要求されるといっても過言でないと思います。
しかし、フィットネスクラブまで必要とされることに少し驚きました。
確かに、運動中に急な体調悪化が起こる可能性もあり、緊急搬送などが必要な場合は、緊急連絡先を求められます。
お話しをお聞きして、私どもが「緊急連絡先」になることを提案しました。
私どもでは、有償ですが緊急連絡先の引き受けを業務としても取り扱っています。
毎月、低額ですが費用をお支払い頂いて、普段の相談のお相手になること。そして緊急連絡先になること業務として取り扱っています。
ここでは、費用を具体的には記しませんが、低額ですので年金生活者の方も負担にはならないと思います。
この相談者の場合は、緊急時に延命措置が必要なのか否か、きちんと書面で表明して頂いてから、緊急連絡先をお引き受けしました。
もし、相談者が救急搬送され私どもに連絡が入った場合は、窓口になって対応することができる範囲で対応を行います。
ただ、このプランでは支払いに対する連帯保証は行いませんので、入院や施設入所には利用できない場合も多いのですが、日常生活の中で必要な大抵のことであれば、この緊急連絡先の引き受けで対応できていると思います。
この相談者の方は、私どもを緊急連絡先としてフィットネスクラブにご入会なされ、通所されることになりました。
老人ホームの見学は必要ですか?(見学同行を通じて感じること)
老人ホームへの入所を考えるにあたり、実際に見学をした方がよいですか?
よく聞かれる質問です。
この質問に対しては、やはり見学はした方が良いと思います。
やはり、パンフレットでは、どうしても分からない施設の雰囲気があり、各施設ごとに雰囲気は明らかに違います。
例えば、同じコンセプトの高級施設でも、実際に建物に入ってみると明らかに雰囲気が異なります。
なぜ、雰囲気が違うように感じるのか。
明確に説明することはできません。そこで働くスタッフさんや、施設長の人柄、あるいは、その場所(土地)が持つ波長か何かなのかも知れません。
そこで働く人たちの意識、無意識の集合体が、その場所の雰囲気を作り出していたとしても、不思議ではないと思いますし、不動産を扱うとわかりますが、その土地、建物と購入者、入居者との相性のようなものは、やはり存在すると個人的に思います。
相談者と見学を一緒にしてみると、「あそこは何となく陰気臭い」とか「なんか、あそこは嫌だ」など、およそ科学的ではない理由を話される相談者も多いです。
一方で、「この施設にしたい」と話されるときは、相談者の顔の表情も明るく、積極的に話されるなど、「ここに決められるな!」と言うのは、私どもが、説得しなくても傍で見ているだけで分かります。
実際に見学したあとで、私どもが入居する様に説得することなどは行っていません。
入所するべき時期に至り、相性が合うところが見つかれば、相談者の方が自ら入所を決断されるからです。
そのような意味では、条件や相性を含めて「的を得た」施設をご案内できるかが、大切になると思います。
そして、機が熟したタイミングで見学されることをお勧めします。
取りあえず見学だけしたとしても、その時期が来ていなければ、見学に際しての感度が低く、参考にならない様に感じます。
相談される方の話をよく聞くこと。相談される方の雰囲気と時期を感じ取ること。
そういう意味では、相談に応じるこちら側もある程度の人生経験が求められるように感じます。
あと何年くらい自分の貯金がもつか?(資金計画からみた老人ホーム探し)
ご高齢の方が、老人ホームへの入所を検討される場合によく不安に思われることです。
老人ホームへ入所するのは良いけれども、自分の貯金で一生やってゆけるのだろか?
不安に思いはじめると、老人ホームへの入所をためらってしまうのもわかります。
今回の相談者も、その様な不安があり、老人ホームへの入所を躊躇しておられました。
その方のご年齢、年金額、貯金額などをお聞きする限りは、不安など無いように思われましたが、やはり自分の貯金が減り続けるのは、精神的に不安なことは理解できます。
そこで、現在の預貯金や年金額、そして老人ホームでの生活費を想定して、あと具体的に何年お金がもつのかを、相談者と一緒にシュミレーションしてみました。
具体的な内容は差し控えますが、この方の場合は、143か月(約12年間)年金収入と預貯金の切り崩しで生活できることが判りました。
これを確認できたことで安心できたのでしょうか。老人ホームへの入所に前向きになって頂けました。
この方の場合は、比較的しっかりとしておられる方でしたから、数字でしっかり示して差し上げることで、ご理解が進んだのだと思います。
この種の相談に応じるためには、相談者が自分の資産内容を他人に教えることになるため、前提として、しっかりとした信頼関係があることが必要です。
私どもを信頼して、ご相談を下さっている方が、「これで安心できた」と満足いただける相談結果になるように気を引き締めて行きたいと考えています。
その中で、一番大切なのは「守秘義務」だと思います。
相談内容を誰かと共有する可能性がある時は、当たり前ですが相談者の同意が必要です。
相談者の家族や、紹介して下さった方、ケアマネージャーさんなど、一見すると相談者のブレーンであっても、相談者本人の同意がない限りは、相談内容を開示するべきでないと思います。
人は、誰しも秘密にしておきたい事や、出来れば知られたくない事の一つや二つあるものでしょう。
そういうことを開示してくれた相談者に少しでも秘密漏洩の不安を与えたくはありません。
相談を受ける仕事をする者にとって「口の堅さ」は、とても大事なことなのです。
もちろん、生命身体に関わるような場合や、窮迫した権利救済が必要な場合は別ですが。
この秘密保持を更にしっかり意識して、気を引き締めて相談にあたって行きたいと思っています。