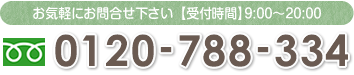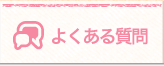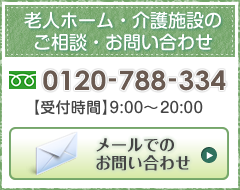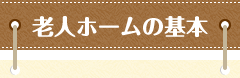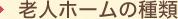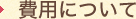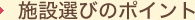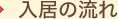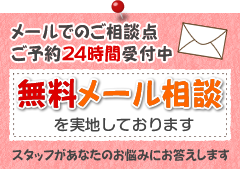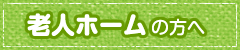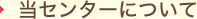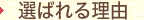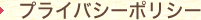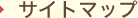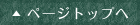ブログ
ケアマネジャーと連携する「身元保証人」の仕事:「違和感」に気付き、伴走型支援で信頼を築く大切さ
本日は、午後から身元保証人として関わる方々との定期的な面会のため、3つの施設とご自宅を訪問しました。効率を考慮し、訪問日は集中的に設定する様に心掛けています。
「違和感」を見逃さないプロの目
お電話でご本人や施設の職員様からお話を伺うだけでも、ある程度の状況は把握できますが、やはり実際に顔を合わせてご本人の様子を拝見することが、何よりも重要だと考えています。
耳から入る情報と目から入る情報に違和感がある場合、それは見過ごせないサインです。例えば、口頭では「順調」と説明されていても、ご本人の身なりや居室が不衛生であれば、その説明だけでは納得できない「何か」が隠されている可能性があります。また、人は困難に直面した時ほど「大丈夫です」と言ってしまう傾向があります。大きな問題が起こる前にその違和感に気づき、対応することが私たちの役割です。
言葉と現実を照らし合わせる丁寧な確認
今回の訪問でも、まずは施設の職員様や担当のケアマネジャー様からご本人の状況を時間を掛けてお伺いしました。そして、ご本人の体調や状態に合わせてお声がけをしました。
私たちが大切にしているのは、言葉と現実が一致しているかどうかです。ご本人の発する気配、雰囲気、身なり、居室の様子が、口頭での説明と合致しているかを見極めます。良い状況なら良いなりに、悪い状況なら悪いなりに、その乖離がないかを確認することで、見守り体制が適切に機能しているかを判断できます。
「山あり谷あり」に寄り添う伴走型の支援
人生も体調も「山あり谷あり」です。上手くいくときも行かないときもあると思います。私たちは、ご本人の状態、事情に合わせて伴走する支援を心がけています。そのためには、私たち自身の人間的な成熟も不可欠です。しっかりと傾聴し、必要な意見は明確に伝えられる、信頼される支援者でありたいと思っています。
”老人ホームの住み替え”はトラブル対応があることを念頭に
老人ホームへの入居は、ご本人やご家族にとって人生の大きな選択です。しかし、一度入居した施設での生活がうまくいかず、**「住み替え」**を検討されるケースも残念ですが存在します。
今回は、病院のソーシャルワーカーさんからご相談いただいた、老人ホームの住み替え事例をご紹介します。
相談のきっかけ:入居者さんのSOS
ご相談者の方はすでに老人ホームに入居されていましたが、**「退院と同時に新しい施設に移りたい」**と強く希望されていました。
詳しくお話を伺うと、
- 十分な介護が受けられていない
- 費用の内訳が不明瞭で不信感がある
といった問題があり、現在の施設生活に不安を感じているようです。
こうした状況から、退院支援を行う病院のソーシャルワーカーさんが「このままではいけない」と感じ、私たちにご相談くださったのです。
住み替えを成功させるための課題
住み替えをスムーズに進めるには、いくつかの課題があります。
1. 新しい施設の選定
ご相談者さんの希望や心身の状態に合った施設を速やかに探す必要があります。住み替えが長引けば、そのぶん現在の施設への家賃などの費用負担が増えてしまうため、スピーディーな対応が求められます。
2. 現在の施設との退去交渉
退去時には、利用料の精算や敷金の返還など、金銭的なトラブルが発生する可能性があります。特に、今回のケースでは、ご家族も第三者の介入を強く希望されており、こじれる可能性が示唆されました。
しかし、老人ホーム紹介会社が金銭や法律に関する問題に介入することは、仮に善意でもできません。そこで私たちは、士業との連携をご提案しました。
【事例のポイント】紹介会社と士業の連携で課題を解決
この事例では、以下の役割分担でサポート体制を構築しました。
- 私たち老人ホーム紹介会社:
- ご本人やご家族の意向を丁寧にヒアリング
- ご希望に沿った最適な施設を迅速に選定・提案
- 弁護士・司法書士:
- 現在の施設との退去交渉や金銭問題の対応
- ご本人やご家族の精神的負担を軽減
この連携により、**「老人ホーム探し」と「退去トラブルの解決」**を同時並行で進めることができます。
まとめ:トラブルを抱える住み替え相談こそ専門家へ
住み替えには、単に新しい施設を探すだけでなく、現在の施設との”ややこしい”交渉を伴うことがあります。
この様な時、ご本人やご家族だけでは解決が難しいトラブルも、老人ホーム紹介会社と弁護士・司法書士が連携することで、スムーズな解決を目指せます。
ケアマネジャーさんやソーシャルワーカーさんが、入居者さんやご家族から住み替えの相談を受けた際は、ぜひ私たちのような専門家にご相談ください。
「このケースは少し”ややこしい”かもしれない…」と感じた時こそ、第三者の介入が必要なサインかもしれません。
老人ホーム入居後のサポート|身元保証から見守りまで、寄り添う意思決定支援の形
身寄りがいない、家族に迷惑をかけたくない…そんなお悩みを抱える方は少なくありません。私たちは、お一人おひとりの「自分らしい意思決定」をサポートするため、身元保証から日々の見守りまで、きめ細やかなお手伝いをしています。
身元保証だけじゃない、私たちが大切にしていること
先日、2年前にご入居のサポートをした女性のもとを訪れました。ご家族がいらっしゃらないため、私たちが身元保証人をお引き受けし、今でも月に一度のペースで訪問を続けています。
定期的な訪問の目的は、単なる安否確認や雑談だけではありません。お話をじっくりと聞かせていただく中で、その方の価値観や性格、意思決定の癖などを深く理解していくことを心がけています。
ある時、この女性から「こんなことがしたい」というご要望がありました。私たちはすぐに動くのではなく、まずそのご要望が「一時的な気の迷いなのか」それとも「本当に叶えたい強い願いなのか」を見極める時間を持ちます。なぜなら、時間を置くことで、ご本人の本当の気持ちが見えてくるからです。
「あなたらしい」考え方を理解するということ
これまでの人生や職業経験などをお聞きすることで、その方の思考パターンや物事を決めるのにかかる時間も見えてきます。すると不思議なことに、「この方なら、こういう風に考えるだろうな」という、ご本人らしい考え方を推測できるようになります。
私たちは、こうした地道な対話を通じて、お一人おひとりの「生き方」を尊重し、意思決定のサポートをしています。単に話し相手になるだけではなく、その方にとって何が一番大切なのかを一緒に見つけ出す、それが私たちの目指す支援の形です。
記録と振り返りが、より良い支援につながる
面会で伺ったお話しの内容や、ご本人の様子はその概要を記録に残しています。こうすることで、考え方の変化や一貫性が分かり、より適切なサポートが可能になります。
終活や意思決定の支援は、単発的な手続きではありません。人生の最終章を、その方らしく豊かに送っていただくために、私たちはこれからも地道な努力を続けていきます。
老人ホーム選びと入居後のサポート。ご家族との関係が希薄な方の訪問サポート事例
私たちは先日、老人ホームにご入居された相談者様のもとを訪問しました。
この相談者様はご家族がいらっしゃいますが、様々な事情で関係性が薄く、普段は連絡を取り合っていないとのこと。しかし、私たちは老人ホームの入所手続きを進めるにあたり、ご家族へ事情を説明し、ご理解をいただくことができました。
ご本人にその旨をお伝えすると、とても喜んでくださり、「ありがとう」とのお言葉をいただきました。
入居後の「見守り」がミスマッチを防ぐ
ご家族との関係が希薄な方は、老人ホーム入居後に何か困ったことがあっても、なかなか相談できないかもしれません。そのため、ご入居から約1か月後、ご様子を伺うために訪問することにしました。
幸いにも、新しい生活に順調に馴染まれ、食事もしっかり摂っている様子。少しふっくらされたように感じました。感想を伺うと、少し退屈な時もあるけれど、快適に過ごせているとのこと。その言葉に、私たちも安心しました。
「傾聴」が問題解決の第一歩
もし、入居者様が不安や不満を抱えていらっしゃる場合、私たちはまずそのお話にじっくり耳を傾けます。それが**「話を聞いてほしい」という気持ちからくるものか、「具体的な解決策を求めている」**のかを見極めることが重要です。
また、ご本人の経済状況や社会背景によっては、すぐに解決できない問題もあります。それでも、私たちは時間をかけて向き合い、**「傾聴する」**姿勢を大切にしています。
「傾聴する」ことは大変なことですが、相談を受ける側(相談員)を鍛えてくれます。
私たちの入居後サポート
もちろん、すべてのご相談者様にこうした対応をしているわけではありません。しかし、特にご家族がいない方や、関係性が希薄な方の場合は、老人ホーム入居後のサポートを意識して行っています。
これは、入居者様と施設の間で起こるかもしれない「ミスマッチ」を防ぐためです。もし、入居者様の権利が侵害されているような事態があれば、私たちが第三者として問題解決のきっかけを作ることもできると考えています。
私たちは、**老人ホーム紹介のプロとして、ご相談からご入居、そしてその後の生活まで、一貫してサポートすることを目標にしています。「ご家族との関係が希薄で、老人ホームを探すのが不安」**と感じている方も、ぜひ一度ご相談ください。